2007/11/25(日)HT7750
HT7750によるステップアップコンバータ
夏ごろ入手していたHT7750をバラックで組んでみた。色々な方が実験されているがこのチップのうたい文句通りの出力100mAは無理なようです。私が実験したかった事はスイッチングダイオードの違いを見たかったのです。
ファーストリカバリーダイオード(1DL41A)やショットキーバリアダイオード(11EQS10)と一般整流用(ERA15-06V1)とでは思っていたよりも雲泥の差が出たが、一般的なスイッチングダイオード(1SS131,1S2076A)でもこの程度の出力ならば結構使えるなぁという結果が得られたのは大きい。
コイルについてもトロイダルコアの100uHとアキシャルリードの100uHとでは差異が見られなかった。他の方が実験されたblogでは22uH辺りが最も出力が高くなるそうであるが、手持ちに無かった。
HT7750の裏技か?オシロのプローブで反応
どんな波形なのかとHT7750のLX - GND間にオシロのプローブを当てるとLEDの光が強くなることを発見した。ならば?と思い、LX - GND間にコンデンサーを入れる事で出力が大きくなることを発見!。パラメータを変えてみると0.033uF辺りがよさそうであった。それも、マイラーではなく、セラミックでなけれならない所がなんとも、怪しいが・・・。
でも、これはブレッドボード上の配線の影響もあるのだろうなぁと思ってはいるが、今回はこれで良しとしよう。
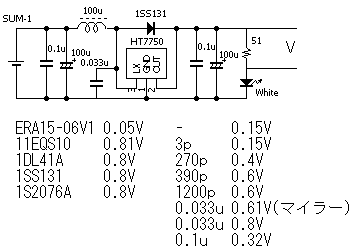
2007/01/10(水)Non-volatile(不揮発) RAM RAMTRON FM1608/FM1808を入手
2006/09/18(月)自転車用フラッシャー
自転車用フラッシャー
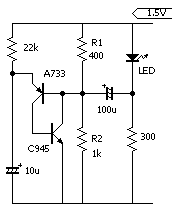
昭和50年代の初歩のラジオかラジオの製作に載っていた自転車用フラッシャーを組んでみた。多分こんな回路図だろうという記憶を頼りに再現すべく取り組む。
確か乾電池1本で一年間光り続けるという内容だったと思う。1.5VでLEDを光らせるためにコンデンサーによるチャージポンプ回路が入っている。そしてそのチャージポンプを発振回路でON-OFFする。この発振回路でまたしても深みにはまって丸一日を費やす。
PNPとNPNトランジスタでPUTを模倣したよくある発振回路であるが、定数が本当にシビアだ。R1とR2は単にバイアスを与えているハズであるが、低い値で設定しないと発振しない。幾つかの雑誌記事に載っている回路ではどれも1Kと470である。これを10Kと4.7Kでは全く動かない。R2を1K固定にしてR1をバリオームで振って見るが動作範囲は非常に狭い。点滅周期は約1HzでLEDが光るのは一瞬である。それ以外のタイミングではこのR1とR2の抵抗が電流を無駄に消費している訳である。あー当時の記事が読みたい。
LM3909ディスコン
元を辿れば、インターネットの話題でLM3909(LEDフラッシャー)のICがディスコンだという話を読んで、そういえばトランジスタでも簡単に作れるだろうと思いついたのが事の始まり。簡単な回路ほど奥が深いのがアナログの世界である。
2006/08/02(水)UART PC16550(PC16550DN)によるシリアルインターフェース
トランジスタ技術の2006年5月号から6502を使ったマイコンボードの連載が始まっていた。興味を引いたのはシリアルポートにナショセミの16550を使っている事だ。

80系でUARTのチップといえば8251が定番であるが、ボーレートジェネレータを内蔵していないのでチップ数を減らす場合には不利だろう。この記事に触発されて最初にした事はこのチップの入手であるが、DIP品種となるとなかなか見つからない。
しかし鼻が利くのかこれまたスンナリと入手。さてこのチップの情報はマイコンで調べるよりもPC互換機には大量に使われているので、その上で走るオープンソース系のOSを調べたほうが早い。
その上、デバイスドライバーのソースコードだけではなく、貴重な説明資料も豊富に見つかる(その上日本語で)。
もちろんこのチップを扱うのは初めてだけれど、データシートも英語だけれどそんなに難しくはないし、実際の
FreeBSD2.8のドライバーのソースなんかも大変参考になるだろう。Cが得意でなくてもinb()とoutb()周りだけ読めればそれでも大抵理解できる。また、現在の物よりも古いソースの方が単純で明快だ。
さて、問題は何に繋ぐかだ。やっぱりここは8048の出番だろうか。PICやAVRではUARTのポートなんて当たり前の事なんだが。
2006/06/25(日)16KbのPROM
小さなメモリー空間

8080AやZ-80そして8048/8035の外付けのROMとして広く使われた2KBのメモリー(P-ROM)。
今となっては2KBというのは猫の額より狭い空間かもしれないけれど、同時期のSRAMに至っては256x4bitや1024x1bitなんていうのもザラでした。
これら3つはintelの2716ピンコンパチブルなので置き換え可能な品種
Xicor X2816BP
XicorのEE-PROM 2816 5V単一で書込み可能 書き込み時間の遅いSRAMと同等に扱える。バイト単位で再書き込み可能(5ms)、一万回保障。100年間のデータ保障。 DateCode 9020
NMC27C16(2716 C-MOS)
National Semiconductor C-MOSの為、消費電流が非常に少ない 80C35と組み合わせて電池駆動可能だろう。DateCode 8424。最近になって、若松通商にて購入した。今でも売っていたのが信じられなかったが。
MB8516(2716)
Fujitsu MB8516 DateCode i2716の富士通版 独特のパッケージです。ピンが折れやすいが金メッキ品です。 DateCode 8103 四半世紀前の物。現在でも問題なく消去・書き込み出来ています。
