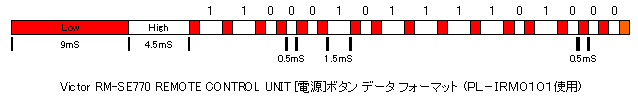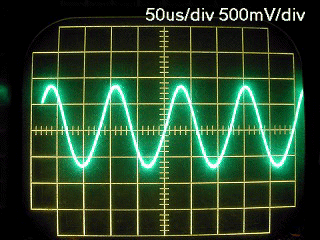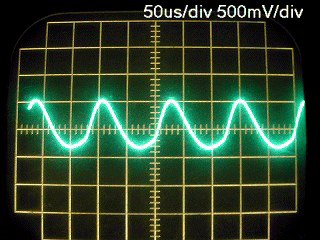2007/02/18(日)クラップ発振回路
クラップ発振回路(成功)
昨日は上手く行かなかったが、回路の定数を至極簡単な物にしたらこちらも発振に成功。家の古いオシロでは高い周波数を上手く捕らえられないが可聴周波数なら問題ない。今まで本の内容を頭の中で自分なりに理解してきたが実際に自分で聴いて、そして観る事でで理解できることは楽しい
発振波形は今まで活字で言われてきたようにコイル部分(A点)の方がエミッタ点(B点)よりも綺麗なものであった。
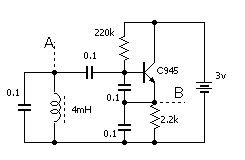
2007/02/17(土)聞こえない音
クラップ発振回路
最近は手を動かしていない。その割りにネットの通販でパーツを物色したり、オークションを詮索している。今日はブレッドボードで何か作ってやろうと思い、さて何がいいかなぁと考えるがアイデアが浮かばない。パーツボックスを漁っていると前に購入しておいた4mHの小さなマイクロインダクタを見つける。レフレックスラジオ用にマルツ電波で買ってきたままの状態だった。
パスコンでよく使われる0.1μFと組み合わせると共振周波数は約8KHzだ。なら発振回路を作ろうと思いつき、クラップ発振回路を組むが上手くいかず、一旦これは諦めて「金属探知機 回路図」でググる事とする
驚愕の簡単回路
どうも、発振回路というとFMワイヤレスマイクで使う、変形コルピッツ回路とディップメータで使われるクラップ発振回路しか思い浮かばなかったが、こんな簡単な回路で発振するとは今まで知らなかった。目から鱗だ。教科書に書かれているコルピッツ発振回路の基本形に抵抗を一本足しただけの単純な回路。
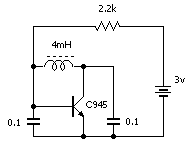
大人には聞こえない
計算上は可聴周波数範囲のハズだからと、クリスタルイヤホンを繋ぐが音は聞こえない。・・・・・
いや隣にいた6歳になる娘が反応している。「なんかイィーって言ってる」と・・・
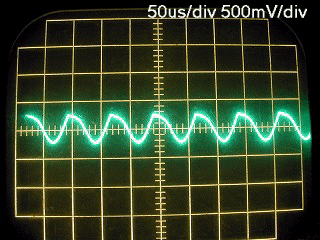
まさか?家の古いあてにならないオシロを繋ぐと確かに発振している。そう回路図を見ると判るがコンデンサで分割されているので発振周波数は予定の倍の15kHz前後なのだ。このくらいの周波数になると大人では聞こえずらいのである。クリスタルイヤホンを耳に当てると確かに高い音が聞こえる。しかし隣にいる娘はイヤホンを耳に入れなくても十分に聞こえるらしい
しかし発振波形はお世辞でも綺麗とは言えないが。
2007/01/30(火)1.5V LEDフラッシャー その2
弛張発振回路
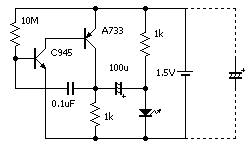
前回作ったLEDフラッシャーには納得できないまま過ぎたが、「エレ工房さくらい」さんのページに1.5VLEDフラッシュキット(商品番号250K-0006)を発見して驚愕。
こちらで用いている弛張発振回路も有名。なぜ前回は、自分の中では昔から使っているこの弛張発振回路を思い出せなかったのかと。
そこで追試を早速行う。オリジナルは3石だが、これを2石に変更し発振定数は最初に見つかった1.5MΩ(なにせ10MΩなんてやたらとパーツ箱にあるとは思えない。)と0.1μFとしてとりあえずブレッドボードに向かうがあえなく撃沈。なぜか発振せず。が、C945のベースを指で触ると発振が起こるというアナログにありがちな不思議な現象に遭遇。
そこで、なんとか10MΩを探すべくありったけの箱をひっくり返し探し回ると偶然にも発見(夜の11時に10MΩが見つかることが驚きだが)
で、定数をオリジナルの10MΩとするとこれがスンナリと発振を繰り返す。
弛張発振回路の奥深さ
ところで、同じ回路でA733のコレクタ負荷をスピーカーに変えると、10KΩだろうが1.5MΩだろうが発振を起こす。この回路は昔から自分が慣れ親しんだ物だから当然だが、負荷を純抵抗にしたとたんこんなにてこずるとはトホホ。本当は1MΩと1μFとか100KΩと10μFというありがちな部品定数にかえたいんだけれどなぁ。
新たなる疑問が
回路を元に戻して、暫くLEDがピカピカするのを眺めていて(既に時計の針は0時を過ぎている)何気にパスコンのつもりで電源に100μF程度のコンデンサーをパラってみると発振周期が早まる事を発見。同時にLEDの光り具合も暗くなるのはなぜ?
ブレッドボード配線だから?それとも電源インピーダンスの影響?再び眠れない日々が続く・・・
1月31日(解決)
上記のパスコン問題は解決した。LEDとA733の間の電解コンデンサーの容量を47μFに減らすと、パスコンの有無によって動作が変わる問題が解決した。やはり「エレ工房さくらい」さんのオリジナル回路にある3石目のバッファーには意味があったのだ。はぁー奥が深いなぁ。
2006/09/18(月)自転車用フラッシャー
自転車用フラッシャー
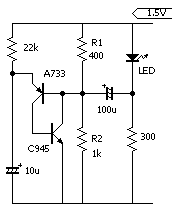
昭和50年代の初歩のラジオかラジオの製作に載っていた自転車用フラッシャーを組んでみた。多分こんな回路図だろうという記憶を頼りに再現すべく取り組む。
確か乾電池1本で一年間光り続けるという内容だったと思う。1.5VでLEDを光らせるためにコンデンサーによるチャージポンプ回路が入っている。そしてそのチャージポンプを発振回路でON-OFFする。この発振回路でまたしても深みにはまって丸一日を費やす。
PNPとNPNトランジスタでPUTを模倣したよくある発振回路であるが、定数が本当にシビアだ。R1とR2は単にバイアスを与えているハズであるが、低い値で設定しないと発振しない。幾つかの雑誌記事に載っている回路ではどれも1Kと470である。これを10Kと4.7Kでは全く動かない。R2を1K固定にしてR1をバリオームで振って見るが動作範囲は非常に狭い。点滅周期は約1HzでLEDが光るのは一瞬である。それ以外のタイミングではこのR1とR2の抵抗が電流を無駄に消費している訳である。あー当時の記事が読みたい。
LM3909ディスコン
元を辿れば、インターネットの話題でLM3909(LEDフラッシャー)のICがディスコンだという話を読んで、そういえばトランジスタでも簡単に作れるだろうと思いついたのが事の始まり。簡単な回路ほど奥が深いのがアナログの世界である。
2006/07/02(日)リモコンのデータフォーマット
赤外線リモコン RM-SE770

就職してから直ぐに買った物の中に、オーディオコンポがあった。ビクターのロボットコンポというやつでレコードプレイヤー・チューナー・タイマー・スペアナ・グライコ・ダブルカセット・CDプレイヤー、そしてアンプとスピーカーがセットになっていた物で総額30万円くらいだったと思う。それを確かローンを組んで買ったと記憶している。で、これは全部お払い箱で現在はそのスピーカーとリモコンだけが何故か手元に残っている。
[Z80]データフォーマット PL-IRM0101使用
解析結果はご覧の通り割と単純ですね。ちなみに一昨年のこの日記を書いて以降ずーっと今日まで机の上にZ80のボードが放置されていた。どうりで片付かない訳だ。